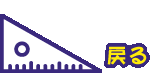彰は、1時間前の医者の言葉に、もはや己の精神tが持たない状況に追い込まれていた。それでもあと1時間以内に決断を下さなければならない。
「・・・お気の毒ですが、母子ともに極めて危険な状態にあります。二人とも救かる可能性は20%あるかどうか・・・」
「どちらか一方をと言うのでしたら、何とかなるかもしれませんが」
「酷なようですが、奥さんを救けるか、生まれて来る子どもさんを救けるか、どちらかを選ぶしかないと思います」
医者の言葉は、人道的にはこの上もなく残酷なように思えたが、現実問題として、医者のとるべき立場としては、極めて正当なものなのであろう。患者からの信頼が厚い医者であることも前々からわかっていた。それでも彰にとっては神経がすべて遮断されるような選択を迫られていた。
彰と裕美は夫婦である。彰42歳、裕美36歳、結婚5年目にして待望の子どもを授かるはずだった。
出産予定日まであと20日ほどという日に裕美が交通事故に遭ったのである。入院中一人暮らしをしている彰の不便を慮って外出許可をもらい、アパートに帰ろうとしたとき、不注意で車にはねられてしまったのだ。たまたまその場所が入院している総合病院のすぐ近くだったので、裕美は救急車で同じ病院の救急治療室に搬送された。
彰が病院から電話をもらって妻のもとにかけつけたとき、彼女にはもう意識はなかった。すぐに手術をしなければ生命の維持は難しい状況にあった。当然その場で手術ということになるのだが、裕美の体には出産を20日後に控えた子どもがやどっていたのである。裕美を救うために手術をすれば、胎児を殺してしまう可能性が極めて高いのだ。
こういうとき、ごく自然な選択をすれば、まだ見ぬ子どもよりも実在する妻を助けることが正しいことなのかも知れない。でも二人には待望の二世であり、果たして、「お前を助けるために子どもを犠牲にした」と言えば、裕美は正常でいられるだろうか。自分の死よりも悲しむかもしれない。それが母親というものであろう。
彰にのこされた時間はあと1時間弱であった。それ以上時間が経てば二人とも死んでしまう。
彰と裕美は境遇が非常に似通っていた。彰は幼い頃、相次いで両親に病死され、母方の祖父母に育てられた。中学校を出てからは働きながら夜間の高校へ通った。高校を卒業するまではその家で住まわせてもらい、卒業と同時に安いアパートを借りて一人暮らしを始めた。その祖父母もいまはもうこの世にいなかった。父方の親戚とはもともとほとんど行き来がなかったが、その二人もとうに亡くなっている。全く親戚がないという訳ではないが、ほほ天涯孤独といってよかった。
一方、裕美の方は、彼女が幼い頃両親が離婚し、母親にひきとられて大きくなったのであるが、その母親は、彰と裕美が出会う少し前に病気で亡くなってしまった。父親の方は商売に失敗して失踪し、未だに行方はわからないが噂ではとうに死んでいるらしい。
彰が高校を出て10年経った頃、二人は出逢った。彼がよく食べに行く定食屋で裕美はウェイトレスをしていたのだ。お互いに相手に自分と似た匂いを感じた二人は、どちらからともなく声をかけるようになり、休日にデートを重ねた。出会いから1年ほど経った時に、彰の方から求婚したのである。ともに家族の愛情に恵まれなかった二人は自分たちの子どもを熱望したが、なかなか恵まれず、5年してやっと授かろうかというときの裕美の事故だったのである。
裕美は自分が入院している間不便であろう彰のことを慮り、外出許可をもらって家に帰ろうとしたのであるが、病院を出てからすぐにタクシーには乗らず、病院近くのスーパーに寄ったのだ。そこで彰の身のまわりの物やちょっとした食料品を買って一度店を出たのであるが、買い忘れのあることに気づいてスーパーに戻ろうと急いだときに車にはねられたのである。裕美は頭を強打した。CTスキャンの検査では明らかに打撲による影響で、脳内の血管の一部が損傷していた。大至急手術をしなければ血管が裂けてしまう危険があったのだ。
不幸中の幸いか、今のところお腹の胎児には影響がないようだ。しかしながら脳の手術となると当然全身麻酔である。これが一番怖い。局所麻酔の場合は、胎児への影響はほとんど心配ないのであるが、全身麻酔となると、母胎の血中濃度が上昇し、最悪の場合には胎児を死に至らしてしまうし、奇形児となる場合もある。
あと20分ほどでもう一度担当医がやって来る。それがタイムリミットなのだ。彰は様々な思いが交錯する中にもようやく決心がついた。
「俺には、やはり、どちらを選ぶなんてことはできない。20%未満の可能性かもしれないが、それに賭けよう。裕美もきっと許してくれるはずだ」
彰はそう決心した。これが仮に、裕美の方に両親なり片親なりがいたとしたら、事態はさらに困難を極めていたであろう。だが、幸か不幸か裕美には俺しかいない。俺だけが決断しなければならず、そして俺だけに決断が許されるのだ、そう彰は自分に言い聞かせた。
このとき、彰は既にある覚悟も決めていた。もし、最悪、二人とも亡くなってしまったら俺も死のうと。その考えが、正しい、正しくないはわからない。だが、まず、ほとんどの人はそれほどまでの決断を迫られることはないのである。このときの彰に誰がどんなアドバイスを与えられるというのか。彰はそう決心した。それだけが事実であった。
彰の覚悟を聞いた医者はもう何も言わなかった、いや、言えなかった。それになにより時間がないのだ。
「わかりました、最善は尽くします。だが最悪の場合は、覚悟しておいてください。そして、形式的なことで申し訳ありませんが、この同意書に同意ください。そうでないと手術はできません」
無論、彰は同意した。手術が始まった。
手術中のランプが点灯してからもう2時間が経った。彰は、手術が始まってからも何度も自問自答した。
「俺の選択は正しかったのだろうか・・・」
しかしながら、何度自分に問いかけてみても答が返ってくるはずなどなかった。昔読んだ本の中に、
「決断というものは下すまでは大変だが、一度下してしまえば何ということはない。あとはそれに従って行動するだけだ」
そんなふうな言葉が書かれていたのを思い出した。
「勝手なことを書きやがる。人間そんなに強いものじゃないだろう」
彰は、昔それを読んだときには結構納得できるものとしてとらえていたつもりだったが、今はただむなしい机上論にしか思えなかった。
決断を迫られているときには、あれほど短く感じた時の流れが、手術が始まってからは途方もなく長く感じられた。彰はじっと目を閉じて、自問自答するのをやめた。脳裏では、裕美と暮らし始めてからの5年間の思い出が走馬燈のように駆け抜けていった。彰は、裕美のことを「自分には出来すぎの女房だ」と思っていた。たいした稼ぎもなく、新しい服なんか何一つ買ってやれないのに、愚痴一つ言わず、俺について来た。家計を助けるためにパートにも出て働いた。家族の温もりに恵まれなかっただけに、人を思いやる気持ちが誰よりも強かったのだろう。
彰の涙腺は、液体が流れ出るのを止めることを潔しとしなかった。声を殺して泣いた。とめどもなく涙があふれ出てきた。20分ばかりそれが続いた。
手術開始から4時間ほど経ったとき、「手術中」の赤いランプが消えた。彰は思わず立ち上がった。ほどなくして、ストレッチャーにのせられた裕美が手術室から出てきた。周りには数人の看護師さんたちがストレッチャーを取り囲むように付き添っていた。点滴を持っている人もいた。これから集中治療室へ移るのだ。
少し遅れて執刀をされた先生が出て来た。担当医である。彰の前に歩み寄ってきた。彰は、「先生、どうでしたか?」その声が喉元まできていたが、どうしても声にならなかった。聞きたい気持ちと聞くのが怖い気持ちが狂おしいほど交錯していた。そんな彰の思いを察したかのように、先生が口を開いた。
「うまくいきました。母子ともに大丈夫です。この種の例としては、奇跡にちかいことかも知れません」
担当医のその言葉に、彰はまたしても声が出なかった。本来ならば何をおいてもまず、「有難うございました」であったろう。そんな常識すら失せてしまうほど彰は感極まっていた。担当医の言葉が続いた。
「手術そのものは2時間半ほどで終了していました。ただ、手術前にも申し上げましたように、麻酔薬の投与による母胎の血中濃度の上昇、これが一番怖かったので1時間以上、経過を見守りました」
「この判断には、私の勘も入ってきます。勘などというと、好い加減な、と思われるかもしれませんが、医学といえども決して万能ではありません。科学そのものがそうだと言ってもよいでしょう。しかしながら未だ解明されていない事柄に出くわしたときや、深刻極まりない状況下にあるとき、本当に必要なものはそれに対峙する者の勘だと私は信じています」
担当医はきっぱりそう言い切った。彰にはそれが神の声のように思われた。やっと気持ちが落ち着きかけた彼は、
「先生、有難うございました」
と丁重に礼を述べた。
「勿論、予断は許されません。もう、これで100%大丈夫と思われるまで我々スタッフも万全の態勢で臨みます」
そう言って、担当医は医務室の方へ歩いて行った。彰は、その後ろを姿を見守りながら、深く一礼をして集中治療室へと向かった。
-了-