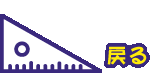

『僕のジーンズ物語』-桒原聡-
一人の若い男が船に乗っている。その船は豪華客船と言うほどのものではないが、さりとて、小さな船でもない。船縁(ふなべり)の手すりにつかまって海を眺めていた男は、やおら、上着のポケットからチョコレートを取り出し、首を少し傾けながら、気障(きざ)ともとれる感じで、それを一口囓(かじ)った。いかにも二枚目風な男の容貌と、その仕種(しぐさ)が絶妙にマッチしていた。 これは昭和四十年代にテレビで流されたコマーシャルの一場面である。四、五十代以降の年齢の人であれば、ご記憶のある方も多いのではないか。船に乗った二枚目の男というのは、俳優の近藤正臣であった。彼はこの頃本業の方でもニヒルな役を演じることが多かったように思う。当時小学生であった私はこのコマーシャルの前で釘付けになった。しかしながら、近藤正臣に夢中になったわけではないし、チョコレートや船に心を奪われたわけでもない。
私を虜(とりこ)にしたのは彼が身につけていた上着とズボンであった。白い上着に、白いズボン、そのときの彼の出立ちを三十年以上たった今でも私は鮮明に思い浮かべることが出来る。世の中にこんな恰好のいい服があるものかと驚き、また、それを見事に着こなしている近藤正臣にも、役者のセンスを認識させられた。上着はGジャン、ズボンはジーンズといい、今では若者は言うに及ばず、子供から年配の方にまで絶大なる支持を受け、市民権を得ている衣服である。特にジーンズの方はジーパンとも呼ばれ、これを知らない人は多分いないものと思われるが、当時はまだ珍しいものであった。そして、ジーパンを穿(は)いている人は肉体労働をしている人か、若い人では少し不良っぽい人が多かったような記憶がある。 ただ、そのコマーシャルを初めて見たときには、私はまだジーパンのジも知らなかった。それを知ったのは、学校の休みの日に、偶々(たまたま)叔父の家へ遊びに行ったときだ。叔父と一緒に居間に寝そべってテレビを観ていると、例のコマーシャルが映し出された。このときとばかりに、私は尋ねた。
「おじさん、あの人が着ている上着とズボンは何て言うの」
叔父は上着のことは知らなかったようで、 「ジーパンや」 とだけ答えてくれた。
それからというもの、私の頭からジーパンという言葉が消えることはなかった。勿論、まだブランドなどという概念はなく、ただジーパンが欲しい、それだけであった。
そして、とうとうそれを穿くことのできる日がやって来た。小学校五年生のときだったと思う。あまりにも私がジーパンのことばかり言うので、見かねた親が買ってくれたのだ。ところが、実物を目の当たりにした私は愕然となった。それは、あの近藤正臣が穿いていた白いものとは全くの別物だった。
「こ、これ、ジーパン?」
「そうや。欲しかったんやろ」
「嘘や。こんなん、隣のおっちゃんが穿いている仕事着やんか」
「阿呆やなあ、これをジーパンというんやがな」
母は他のことをしながら幾分たしなめるような口調でそう言った。 「こんなんジーパンちがうよ」 と心の中では思いながらも、自分のためにわざわざ洋品店で買ってきてくれた母のことを思うと、それ以上は何も言えなかった。 「叔父さんも叔父さんや。白いジーパンと言ってくれたらよかったんや」 と叔父に対しても不満な気持ちを抱きながらも、これまた、いつもたいそう可愛がってくれるので、文句を言う気持ちにはなれなかった。子供の頃の私はどうもそういうところは妙に大人びていたというか、気持ちを抑え込んでしまうところがあったようだ。
仕事着と思っていたジーパンであるが、実際穿いてみると、うまくは表現できないが、悪い感じはしなかった。何か自分が少し大人になったような気がした。サイズもぴったりであった。さすがに母親というものは息子の体の大きさを十分把握しているものだと感心し、また、後(のち)にではあるが、母はジーパンを買うにあたり、私の他のズボンを洋品店まで持って行って、サイズを合わしてくれたことも知った。彼女は洋裁の仕事をしていたので、その向きのことは得意なのでもあったろう。そういうことも知るにつけ、最初は不本意だったジーパンとやらが、私の心の中で宝物に変わっていくのに、そう時間はかからなかった。
大人に対しては遠慮がちな私であったが、学校ではガキ大将もいいところで、よく喧嘩もした。勝手なものである。ジーパンを穿いていることが嬉しくてならず、誰彼なく、その自慢をした。
「おい、正人。お前、このズボン何て言うか知ってるか」
「知らん。何て言うんや」
「阿呆。お前何も知らんのやなあ。これはやな、ジーパンていうんや」
「ジーパン?」
「そうや。有名な映画俳優なんかも穿いているんやぞ。恰好ええやろ」
「そうかなあ。それ仕事着ちがうんか。うちのお父さん仕事のとき穿いてるで」
「仕事着?こら、泣かすぞ、お前」
万事こういった調子である。同級生が私のジーパンのために大いに迷惑を被ったことは言うまでもない。当時の私は、井の中の蛙とはいえ、学年では相当腕力が強く、一学年上の六年生ともしょっちゅう喧嘩をしていた。村の相撲大会では中学生の部に出されたこともある。さすがに中学生は力も強く、私は入賞することはできなかったが、このときの私の相撲を見ていたある中学校の先生が二年後私に柔道部への入部を勧める、という因縁のできた大会でもあった。何故、相撲ではなく柔道なのかと言えば、やがて私が入学することになる箕島中学校には、その頃相撲部はなかったのだ。
六年生の終わり頃になると、ジーパンがボロボロになってきた。先に書いたように、学校では毎日のように暴れ回っていたので、当然といえば当然のことであった。私は一念発起して、今度は自分の貯金で、一人で店へ行って新しいジーパンを買うことにした。お年玉やら何やらで貯めてあったお金を握りしめ、私は洋品店へ行った。ただ、一応両親にはその旨(むね)を話し、了解はとっておいた。私が行った店は、前に母がジーパンを買ってきてくれた洋品店であり、家から歩いて五分ほどのところにあった。
「おばちゃん、ジーパン欲しいんやけど」
「ああ、聡ちゃんか。前のんは?」
「うん、ボロボロになってきたんや」
「そうか。家の人には言うてあるんやろな」
「大丈夫、ちゃんと言うてるよ」
「それやったら、よろし。で、どんなん欲しいんや、と言うてもうちは専門店やないさかいなあ」
「ジーパンの専門店なんて、あんの?」
「この田舎にはないけどな、大阪の問屋へ行ったらあるよ」
「ふうん、そうか。それで、おばちゃん今度いつ問屋へ行くの」
「月に1回やから、来月やなあ」
「来月かあ」
「そうそう、この前問屋へ行ったときに見たんやけどなあ」
「何を見たん?」
「あのな、前に聡ちゃんが買(こ)うてくれたのと違う色のジーパンがあるんよ」
洋品店のおばさんのその一言に私は胸の高鳴りを覚えた。テレビで見た、あの白いジーパンが目に浮かんだからだ。
「お、おばちゃん、し、白か」
「な、なんや、この子は。何を興奮してるんや。白いジーパンなんかあるかいな」
「あるで。テレビで近藤正臣が穿いてるやんか」 私は少しがっかりしながらも、やや強い
口調でそう言った。
「それはな、テレビやし、東京の話やろ。東京といっしょにいくかいな」
おばさんの説明は、今考えてみれば少しおかしなところもあるが、当時の私を納得させるには十分なものであった。
「そうか。和歌山の田舎と違(ちご)うて、東京はやっぱし凄いんやなあ」
「白やないけどな、前のジーパンよりもっと濃い色してるんや」
「濃い色?紺色か」
「そうや、濃紺やな。特別な呼び方まであるんやで」
「特別な呼び方?」
「そう、何て言うたかなあ、確か、1回洗っただけの・・・ 、う~ん、忘れてしもうたけどな、何とかウォッシュって言うんや」
「洗う?おばちゃん、ジーパンて新品(さら)から洗(あろ)とんの」
「そうや。そうせんとな、家で洗ったときに仰山(ぎようさん)縮んでしまうんや」
「ふうん、何やようわからんけど、その何とかウォッシュっていうの欲しいなあ」
「ほな、それまで待つか」
「待つ、待つ。そのかわり絶対に忘れんと買うてきてな」
「よっしゃ。二千円程するけど、ええか」
「うん、大丈夫や。ほな、また」
私が母に買って貰った、はじめてのジーンズは、俗にストーンウォッシュと呼ばれるものである。これは、予めデニムを特別な石と一緒に大きな洗濯機のようなもので洗い、本来の濃紺色(インディゴブルー)を少し薄い色にしたものだ。また、石と一緒に洗うことによって、生地に独特のよれ(専門的にはアタリという)ができ、何とも言えないよい感じになる。一方、洋品店のおばさんの言う、 「なんとかウォッシュ」 というのは、ジーンズに興味のある人なら誰でも知っている、ワンウォッシュのことだ。出来上がって、まだ糊のついたままのジーンズを軽く1回だけ水洗いするので、そう呼ばれるのである。こちらの方は、穿き込んでいくことによって自分の好きなように色を落とせ、またアタリを出すこともできる楽しみがあり、ジーンズの中では昔も今も一番人気のあるウォッシュだ。しかしながら、そのときの私は、そういうことを知る由もなく、ただ、「 今度の僕のジーパンは何とかウォッシュや」 と胸を踊らせながら、おばさんが大阪の問屋から買ってきてくれるのを待っていた。
私は和歌山県の有田(ありだ)市というところで生まれた。有吉佐和子さんの名作 「有田川」 の有田である。それは、県の中心地である和歌山市から南へ二十五キロメートルほどのところに位置した、人口わずか三万人ほどの小都市だ。有田川の河口に拓かれていて、紀伊水道へ続く海や、みかん山など、自然には恵まれている。沖合漁業とみかんを中心とした農業などが主な産業である。みかんは、 「有田みかん」 として、全国的にも名が知られており、現在も勢いは盛んであるが、漁業の方は振るわず、かなり厳しい状況にあるようだ。
その漁業を営む父の長男として私はこの世に生を享けた。ただ、私も、そして八つ年下の弟も家業を継ぐことにはならなかった。父が五十三歳という、現在の平均寿命から言えば、かなり若い歳で病死したからだ。尤も、弟の方は兎も角、私はもともと漁業をする気はなかったし、父もそれを強要しなかった。父の死後、漁業権と船を手放したが、私は現在もこの町に住んでいる。大阪の大学に通っていた数年間を除いて、もうかれこれ四十年以上もここを生活の本拠としていることになる。潮騒や浜風は私の子供の頃のままだが、新築される家などは昔とは大きく変わってきている。古い言葉になるが、モダンで都会的な家が多いのだ。個人的には、こういった傾向はあまり好きではない。田舎は田舎の趣をのこしたままの方が風情があってよいと思うのだが、致し方ないことなのでもあろう。
私がジーンズを買って貰った洋品店は、垣内洋品店といい、私の家と小学校のほぼ中間にあった。 「何とかウォッシュ」 のジーンズを注文してからというもの、学校の帰りには毎日のようにその店に寄り、おばさんを閉口させたものだ。
「おばちゃん、まだ大阪の問屋へ行けへんのか」
「また聡ちゃんか。毎日来るなあ。そんな時間あったら勉強しい」
「新しいジーパンのことが気になってしゃあないんや」
「阿呆やなあ、おばちゃんがまだ問屋へ行ってへんのやから、来ても仕方ないやろ」
「それは、そうなんやけど・・・」
「わかった、わかった。来週の火曜日に行くさかいな、水曜日においで」
「えっ、ほんま。来週の水曜日に来(く)んの。ほんまか、おばちゃん」
「ほんまや、おばちゃんは嘘は言えへん。さあ、わかったら早(はよ)う帰って勉強しい」
その日から翌週の水曜日までを狂おしいほどに待ち遠しく思ったのを昨日のことのように憶(おぼ)えている。中学校へ入って、国語の先生から、 「一日千秋」 という四字熟語を教わったときには、他の誰よりもその言葉の意味がわかるような気がした。
ついに新しいジーパンがやって来た。広大な和泉山脈を越え、我が町に来てくれたのだ。水曜日の放課後、野球やら何やら、全ての誘いを断わり、一目散に垣内洋品店に駆け込んだ。
「お、おばちゃん、来たか」
その時も私はかなり興奮していて、このような喋り方をした。幸いにも店内には他に客はいなかった。いや、記憶違いで、ひょっとしたらいたのかもしれないが、私にはおばさん以外は誰も見えなかったはずである。
「ああ、来てるで。これや」
おばさんはそう言って私の前に紺色のぶ厚い布を差しだした。私は早速、それを広げてみた。
「どうや。この前のより濃い色してるやろ」
「うん、濃いなあ。これが何とかウォッシュっていうジーパンか」
「そうそう、問屋の人に聞いたんやけどな、ワンウォッシュっていうそうや」
「ワンウォッシュ?ええなあ。何とかウォッシュよりずっと恰好ええがな」
「考えてみたら何やなあ、一回洗っただけというんで、そう呼ぶんやなあ」
「ああ、そうか。一回がワンで、洗うがウォッシュか」
「どうや、おばちゃんもなかなかやろ」
おばさんのその言葉には私は返事をせず、新しいジーパンを穿きにかかった。
「まあ、勝手なもんやなあ。この子は」 とおばさんは幾分不興げにそう言ったが、私はそれどころではなかった。
このワンウォッシュ、まず手触りがゴワゴワしていて、実際に穿いてみても、前のものよりかなりぶ厚い感じがした。 「これなら少々暴れても破れへんなあ」 と心の中で私はその頑丈そうなつくりに満足した。濃い色合いも一遍に気に入った。ただ、シルエット云々は、まだ子供の私には考えの及ぶことではなかった。通常、この手の店では、裾上げはその日のうちにはしてくれず、大体翌日仕上がりになるのだが、おばさんは特別に二十分ほどで裾上げをしてくれた。私へのサービスか、余程店が暇であったのだろう。私は感激して、
「おばちゃん、おおきに。ほな、帰るわ」
「おいおい、聡ちゃん、それ困るがな。お金は?」
「あっ、そうか。お金がいるんやなあ」
「当たり前やがな、この子は」
おばさんはややあきれ顔であった。しかしながら、困ったのは私の方で、お金を持っていなかったのだ。現在はどうなのかは知らないが、当時私が通っていた小学校では、学校で必要なとき以外はお金を持って行くのを禁じられていた。厳密には学校の行き帰りに何か食べ物を買ったりするくらいのお金でもいけないのだが、その程度ならば大体皆持っていて、規則などないに等しかった。それにしても、ジーンズを買うだけのお金を持って行く勇気はさすがの私にもなく、またそのこと自体完全に失念していたのだ。
「おばちゃん、御免。学校の帰りで、お金持ってないんや。家に帰って持って来るさかい、これ置いといて」
「ああ、そうか。学校帰りなんやなあ。ええわ、ええわ。置いていかんでもええで。お金はあとでもかまへんよ」
この辺の心持ちは田舎ならではのことであろう。おばさんの言葉に甘えて、袋に入れてくれたジーパンを小脇に抱え、私は家に帰った。
家に着くとすぐ、私は自分の部屋に入って貯金箱からお金を出そうとしたが、代金がわからなかった。あきれた話であるが、おばさんもおばさんで、金額を言わなかったのだ。確か先日注文したときに、「 二千円くらいするけど、ええか」 と言っていたのを思い出し、その額より少し多めに持って再び垣内洋品店へ行った。代金は二千円よりほんの少しだけ高かったと思うが、問題のない範囲であった。 家で再度ワンウォッシュを穿いてみた。悪くなかった。前の薄い色の方も勿論気に入っていたが、今度のものはその頑丈そうなところが特によかった。何かそれを穿くと強くなるような気がするのだ。後ろの右ポケットの上のラベルは前のものと同じであった。洋品店の仕入れルートが同じなのであろう。
それからというもの、ほとんど毎日ジーパンを穿いていた。この時期は体の成長もはやく、当然サイズも合わなくなってくるが、親に買って貰ったり、お年玉で買ったりして、穿き継いでいった。買う店はいつも垣内洋品店で、ブランドも同じであったが、私にはジーパンがあればいいのであって、ブランドなどは意識していなかった。ところが、そんな私のジーンズ観を根底から揺るがす出来事が起こったのだ。テレビで初めてジーンズを見たとき以来の衝撃的な出来事であった。
そのとき、私は中学校二年生で、柔道部に所属していた。私が通っていた箕島中学校には、二年前まで柔道部はなかったのだが、丁度私が入学する年に他校から転任して来られた栗山先生が創部してくれたのだ。小学生の私が中学生の部の相撲大会に出たのを見てくれていた先生である。この先生の指導力は群を抜いていた。箕島中学校に来られる前は隣町の湯浅中学校というところで柔道部の部長をされていたが、その学校は毎年県大会に出場し、好成績を収めていたのである。
当時の箕島中学校は、私の通っていた田鶴(たづ)小学校という小さな学校と、田鶴の二倍ほど生徒がいる箕島小学校の、二つの学校の卒業生が入学する公立中学校であった(現在は三つの小学校から来る生徒で構成されている)。恥ずかしい話であるが、その頃、私の村や町では二つの違うものが出くわせば、まず衝突が起こった。中学校でも田鶴小卒と箕小卒が毎日のように喧嘩をする。そういう腕白者の中でも特に目立つ者を集めて、栗山先生は柔道部をつくられた。一年生だけの部員である。厳密にはそれまでにも同好会のような形で柔道をされていた二、三年生もいたが、正式な部となってからは全く稽古には来なかったし、新たに入部を希望する上級生もいなかった。部員は中一の悪ガキだけなのだ。
柔道を始めてからも私の喧嘩癖はあまりなおらなかった。と言うより、 「もっと喧嘩に強くなるために」 という不純な動機による入部なので、何をかいわんや、なのだ。しかしながら、武道の精神でもなおすことのできない私の喧嘩癖をなおすものがいた。
私には中学校に入る少し前から、密かに思いを寄せる、Mという同級生の女の子がいた。私の一方的な片思いであり、彼女はそんな私の気持ちを知る由もなかったのだが、入学して三か月ほど経ったある日、偶々帰りが一緒になった。彼女は陸上部に所属しており、二人ともクラブを終えての帰りで、帰る方向も同じなのだ。私は、思い切って、 「よう」 と声を掛けた。彼女は返事をする代わりに、こう言った。
「聡くん、毎日喧嘩ばっかり、バカみたい」
これはこたえた。言葉が出なかった。当然、帰り道を一緒に、などというような甘いことはなく、彼女はさっさと一人で自転車を漕いで帰ってしまった。私は暫く動くことができずに、その場で考え込んだ。 「そうか、男は喧嘩ばかりしてたらだめなんやなあ」 そう痛感した。以後、自分でも不思議なくらいに小さなことで余り腹を立てることもなくなり、喧嘩癖も徐々になおっていった。思春期の男には武道の精神なんかよりも女の子の一言の方がよっぽど効くようだ。
私たちの柔道部は日ごとに、目に見えて強くなっていった。さすがに一年生のうちは前述の湯浅中学校には歯が立たなかったが、二年生になるとその中学校はもはや私たちの敵ではなかった。先生も三年では全国を狙うと堂々と公言して憚(はばか)らなかった。不運にも二年のときにはレギュラーの一人が練習中に腕を骨折し、県大会では二位に甘んじてしまったが、事実上、我々の相手になる中学校は和歌山県には存在しなかった。
強い相手がいなくては進歩が望めないということで、私を含むレギュラーの五人は放課後、近くの箕島高校柔道部へ稽古に行かされることが多くなった。夏休みの合宿にも当たり前のように参加させられた。その合宿中に私のジーンズ観を変える出来事が起こったのだ。
午後のきつい稽古を終えて、先輩の高校生と一緒に銭湯へ行くときであった。大体皆稽古のきつさもあって私服に着替えるのを面倒がり、ジャージのままで風呂へ行くのだが、高校生の一人、中尾さんという人はそうではなかった。この人は強豪ひしめく箕島高校柔道部の中でも一番の猛者(もさ)であり、体力的な余裕もあったのであろう、ピシっとしたカジュアル姿で決めていた。私は、その中尾先輩の後ろで釘付けになった。視線がずっとその人の尻の方を向いたままなのだ。断っておくが、当時も今も、私には変な趣味はない。その先輩はジーパンを穿いていたのであるが、私が知っているジーパンとは、かなり違うものに見えたのだ。
私の目はまず後ろの右ポケットの上のラベルを捉(とら)えた。革製と思われるラベルには、Leeという太い文字が、焼き印されたように書かれてあった。そして何とそのラベルの内側をベルトが通っているではないか。 「な、なんや、このジーパンは」 私にはそれが痺れるほど恰好いいものに思えた。
「せ、先輩」
「なんやお前、ちゃんと喋れよ」
「中尾先輩、そのジーパンは・・・」
「このジーパンがどうかしたんか」
「いえ、滅茶苦茶恰好いいですね」
そのとき、そばにいた別の先輩が口を挟んだ。
「聡、お前、それでさっきから中尾のケツばっかり見とったんか」
「はあ。いや、尻を見ていたわけではないですが」
「そうか?俺はまたな、お前変な気(け)があるんかなあと思ってたんや」
「変な気なんかないですよ」 と私はやや強めの口調で言った。このやりとりを聞いていた中尾さんは笑いながら、そして幾分自慢げに、 「聡、お前、ジーパン好きなんやなあ。なかなか見る目もあるで。これはなあ、リーいうて、アメリカ製の有名なものなんや」
「ア、アメリカ製?」
他の先輩連中や中学校の部員たちはそういう話にはあまり興味がないようで、さっさと銭湯へ向かいだしたが、中尾さんはもう暫く話を続けてくれた。
「それにな、ジーパンというのは本当の呼び方やないんや。正しくはジーンズって言うらしいぞ」
「えっ、ジーパンって、正しい呼び方じゃないんですか?」
「そうや。これはリージーンズや」
私はそのとき初めてジーンズという言葉を知った。中尾さんの話によれば、ジーンズはアメリカで生まれ、そして、そのアメリカにはジーンズの三大ブランドがあるとのことであった。リーはその三つの中で、どうやら二番手になるらしい。こういうものに順位などがあること自体おかしな話だと思うが、何でも、世界で最初にジーンズを作った会社があり、そこが業界最大手ということであった。そのときにも中尾さんからその最大手の名を聞いていたはずであるが、話の最中でも私の頭の中はリーのことでいっぱいで、他のものは意識の中にとけ込もうとはしなかった。後に嫌でもその名を知ることになる、ジーンズ業界トップのブランドというのは、言わずと知れたリーバイス、そう、あの501で有名なリーバイ・ストラウス・カンパニーのことだ。そして、三つのうちの、のこり一つはウエスタンで名高いラングラージーンズであることは、ジーンズ好きの人なら知っている方も多いと思う。
話が少し横にそれたが、兎に角、そのときの私にはリーバイスもラングラーもなかった。リーしか頭にないのである。リーのどこに痺れたのか。先にも書いたように、第一に、あの後ろの右ポケットの上のレザーラベルである。実際にレザーだったのかどうかはわからないが、そんなことは大した問題ではない。そのラベルに刻印されたLeeというロゴマーク、これが何とも言えず恰好よかったのだ。そして、そのラベルの内側をベルトが通っているのである。つまり、ラベルがベルトループの役割も兼ねているわけだ。現在でこそ、そういうジーンズは他にもあるが、おそらくはリーの真似であろう。当時としては画期的な仕様だったと思う。このことによって、ジーンズとベルトは一心同体となり、絶妙のバランスを醸し出す。そういう意味ではリーのジーンズは、ベルトをすることを大前提に作られているものと思われる。
また、全体のシルエットも素晴らしかった。私がこれまでに穿いてきたものより幾分太めで、武骨な感じがした。これが私にはたまらなかった。今でも私は男の穿くジーンズは武骨であるべきだと考える。当時の私は武骨という語彙を持ち合わせていなかったが、感覚でそう捉えていた。勿論、こういうことは本人の好みの問題であり、他人に強要することではないのだが。
こうなると、私はリーのジーンズが欲しくて、欲しくて、たまらなくなる。どうしても欲しいものがあると夜も眠れなくなる質(たち)なのだ。中尾さんの話では、リーは有田市近辺では売っている店はないが、和歌山市まで行けば二、三軒あるとのことだった。そのうちで国鉄の和歌山駅に一番近い店を教えて貰い、メモしておいた。ただ、合宿中は日曜日も稽古があるので、買いに行くとしたら合宿が終わってからであるが、買う金がなかった。
リーのジーンズは当時私が穿いていたものより二千円くらい高かったように思う。金の方は、 「おじいさんにねだろう」 と考えた。アルバイトでもしてお金を貯めてからなどとは決して考えない。欲しいものは欲しいときに欲しい。子供とはそういうものであろう。それに、毎日柔道の稽古に明け暮れていて、アルバイトなどする時間は到底なかった。お年玉を待つにしても、まだ夏の真っ直中であり、正月まで待っていたら病気になってしまう。それでは、私はどうやって、おじいさんにねだったのか。 「お年玉の前借り」 という手を使ったのだ。前借りという概念自体は子供の私にはなかったが、したことは正(まさ)しくそれであった。孫というものはことのほか可愛いものらしく、おじいさんは小言を言いながらも、嬉しそうな顔でお金をくれた。
そんなこんなで、中尾さんのジーンズを見てから二週間ほど後の日曜日の午後、私は和歌山行きの列車に乗っていた。箕島から和歌山までは距離にして二十五キロメートルくらいしかないが、当時の国鉄はまだ電化されておらず、一時間ほどかかった。田舎の中学生には、ちょっとした 「旅」 であったが、これまでにも友人と一緒に参考書などを買いに行ったことがあったし、教えて貰った店の位置もほぼ頭に入っていたので、何の心配もないはずだった。そんなことより、 「よし、これで今日リーのジーンズが自分のものになるんや」 という嬉しさの方が遥かに大きかった。しかしながら、ことは、そうスムーズにはいかなかった。生来の喧嘩好きに起因する揉め事が起こってしまったのだ。
和歌山駅で列車を降りた。店までは歩いて五分ほどで、あっけなく目的地の前まで辿り着いたが、その店の前に中学生か高校低学年と思(おぼ)しき、いかにも柄の悪そうな連中が二、三人いた。その頃、和歌山市内では地元の中、高生と、田舎から遊びや買い物に来た、同じくらいの年齢の者との間で頻繁に喧嘩騒ぎが起こっていた。 「まずいなあ、鬱陶しいことになれへんかなあ」 私はそう思いながら連中の横を通って店に入った。店には店主と思われる中年のおじさんと、店員らしい若い女性がいた。日曜日の午後ではあるが、偶々なのか他には客はいなかった。
「おじさん、リーのジーンズを欲しいんやけど」 私は普段の田舎言葉のまま、そう言った。ところが、おじさんの返事よりも早く、私の背後から、
「おい、田舎者(いなかもん)がリーのジーンズを穿いてどうするんや」 という声が聞こえた。
私は思わず振り向いた。そして、驚いたことには、店に入る前には二、三人のはずだったのが、五、六人になっていた。多分私を田舎者呼ばわりした者であるが、その男が私に、
「おい、お前今なあ、店に入る前に俺にメンチきったやろう」 といきなり難癖を付けてきた。 「メンチをきる」 といのは、関西の独特な言い方であり、 「顔(がん)つける」 つまり、敵意のある目で睨みつける、という意味である。勿論、私にはそんな覚えはなかった。こういう奴らが喧嘩を吹っかけるときの常套手段なのだ。懸念していた通り、鬱陶しいことになったと思いながらも、黙っているわけにもいかず、
「いいや、別にそんなことはしてへんよ」
私は無駄なことだとは思ったが、一応そう言った。
「阿呆、してへんことあるかい。ちょっとこっちへ来いや」
先ほどからこう私にまくし立てる男は、どうやらこの中のボス格なのであろう。他の者たちは黙っていたが、この男よりも貫目が下だというのが明かであった。そのとき、はじめて店のおじさんが口を開いた。
「慎治、またお前か。お前らいつもなんやかや言うて他所(よそ)から来た人に喧嘩吹っかけてからに」
ボス格の男は慎治という名のようであったが、店のおじさんにも食ってかかった。
「おっさん、何も知らんと他所者(よそもん)の味方するんか。こいつ店に入る前に俺を睨みつけたんやぞ」
「嘘言うな、お前らいつもその手で暴れるんやないか」 と、おじさんが言うと、慎治の後ろにいた男が、
「嘘やないわ、俺ら全員、こいつが慎ちゃんにメンチきるの見たんや、なあ、皆(みんな)」
他の者たち全員がその通りだと言わんばかりに、おじさんを睨みつけた。ちょっとした愚連隊そのものであった。さすがに大人であるおじさんも、こうも全員に絡まれては怖じ気づいたのか、次の言葉が出なかった。店員の女の人はおじさんの後ろに隠れるようにして、ブルブル震えていた。これはもう警察でも呼ぶか、私が彼らの言う通り、外へ出て袋叩きに合うしかないように思えた。謝って済むような連中でないのは明かであったし、私もそんな気は毛頭なかった。ここら辺がどうも私のまずいところなのだろうか。悪くもないのに謝るのは絶対に嫌だった。ボス格の男がさらに追い打ちをかけてきた。
「おい、お前、こっちへよう来(こ)んのか。この腰抜けが」
吹っ切れてしまった。ここまで、何とか事を荒立てずに済ませたいと思い、正直、大人のおじさんにも期待をしていたのだが、相手の質(たち)が悪すぎるようだ。おじさんは、どう対処してよいものか困惑しているようだし、女の人は震えたままだった。私自身は、もう完全に頭に来ていた。久しぶりのことである。親の心配や、学校のことなどを考えたら、こんなところで喧嘩などをするべきでないのはわかっていた。大体、和歌山へはリーを買いに来たのであって、喧嘩を買いに来たのではない。しかしながら、もうどうしようもなかった。私はおじさんに目で合図をして、外に出る意思を伝えた。ただ、おじさんがどうとったかはわからなかったが。
「お前ら、どうしても喧嘩吹っかけな気済まんのやろ。買(こ)うたらあ」
私はそう言って、連中の前にゆっくりと歩き出した。勝てる見込みはなかった。サシでやるのなら、こんな奴らに負ける気はしなかった。経験上、相手が自分より強い、弱いは、大体見当がついたし、普段柔道の稽古でごっつい高校生に揉まれているので、それに比べれば体格も大したことなく、たやすい相手であった。しかしながら、こういう奴らは、まずサシ、すなわち一対一ではやらないし、仮にサシで闘ったとしても自分らの大将が形勢不利になれば、必ず加勢してくるのだから、どっちみち結果は同じであった。それでも闘うしかなかった。
ただ、勝負というものは、たとえ負けるにしても、その負け方が問題なのだ。簡単に勝たせてはいけない。何とか一泡吹かせてやろうと思った。それには他の者には目もくれずに、ボスだけを徹底的にやっつけることだ。できるだけ短い時間で、しかも圧倒的に敵の大将をやっつけてしまえば、うまくいけば他の者たちは怯(ひる)んでかかってこないこともありうるのだ。それには先手必勝しかない。私が奴らの方へ歩き出すと、慎治という男は一瞬私に背を向けた。ここぞとばかりに私はその男に後から体当たりをかました。男はもんどりうって倒れた。間をおくことなく、私は男の背後に回り、自分の右腕を相手の首に巻き付け、左腕でその右腕をロックした。プロレスや最近流行(はやり)の総合格闘技の試合でよく見られる、スリーパーホールドという技である。柔道では裸締めといった。これは私の得意技の一つなのだ。一瞬呆気にとられていた他の連中のひとりが、
「きたねえぞ、こいつ」 と罵った。
きたないも何もない、喧嘩はそれを承知したときから既に始まっているのであり、隙を見せる方が愚かなのだ。それに大体が一対多の闘いではないか。確かに、素人相手に柔道の技をつかうのは多少は気が咎(とが)めたが、こっちには余裕がないのだから仕方のないことだと自分に言い聞かせた。後にそのことで部長にはこっぴどく叱られたが。
男をそのまま落としてしまうのは簡単であったが、私は一瞬躊躇(ちゆうちよ)した。今度は私に隙が出来てしまったのだ。男はゲホゲホ言いながらも最後の力を振り絞って、腕を振り、救援を求める仕種をした。それを合図に、一瞬たじろいでいた他の奴らが一斉に飛びかかってきた。ひょっとしたらかかってこれないのでは、という私の思惑ははずれた。こいつらにもそれなりの面子(めんつ)はあったようだ。私は男の首から腕を解き、応戦する態勢をとった。この男はうっちゃっておいた。どうせ暫くは動けないのだ。
この後の闘いは、最初からわかっていたことだが、形勢不利もいいところだった。私は相手を絞ろうとしたが、その間にも何発か殴られ、蹴られた。ただ、袋叩きという程でもなかった。私も相手を突き飛ばし、殴りつけて応戦した。最初のうちはそこそこの闘いであったと思う。しかしながら、徐々にスタミナも切れだし、二人がかりで後ろから羽交い締めにされた。息を吹き返した慎治が私の前に立ちはだかり、顔面に一発たたき込んだ。鼻の下にもろにくらい、血が飛び散った。他の者にも二、三発顔や腹を殴られ、意識が遠のきかけた。
丁度そのときであった。私を殴ろうとしている男と私の間にジャージを着た男が割り込んできた。さらに、後ろの方から、
「こらあ、お前ら何をしてるんや。やめえい、やめんか」 という大人の男の声が聞こえた。三、四人いたが、警察のようではなかった。 その男たちは五人と私を引き離し、間に立ちふさがった。店のおじさんが呼んだ、N中学校の教員であった。どうやら五人はその学校の二年生と三年生であるようだ。ボス格の慎治は三年生であろう。
おじさんがN中学校へ電話をしたところ、日曜日でクラブの監視に来ている先生一人しかいなかったのだが、その先生がさらに電話で慎治の担任および他の先生を呼び集めたのだ。私の前に割り込んできたジャージを来た人が、クラブの監視に来ていた先生である。
いつの間にか、私たちの周りは野次馬の人だかりになっていた。教員たちは、店のおじさんの承諾を得て、私たちを店の中に入れた。五人ももう暴れようとはしなかった。慎治の担任が言った。
「慎治、お前、何度言ったらわかるんや。今度騒ぎを起こしたら鑑別所行きやと言ってあったやろ。何や、これは」
「俺は悪ないぞ。先に手出したんは、こいつや」
慎治がそう言うと、他の四人も同調した。
確かに、慎治の言う通り、先に殴りかかったのは私であったが、喧嘩を売ってきたのはこいつらであり、その辺を説明しようとしかけたところ、その先生は、
「大体のことは聞いているし、見当もつく。しかし、君も君だ。暴力はいかんやろ」
暴力も何も、こっちは難癖をつけられ、やむにやまれず、したことであり、その先生の言葉には承伏しかねたが、大きな騒ぎを引き起こしたのは事実で、それに教員三、四人を前にしては、反論もしにくく、黙っていた。
「一応、君の氏名と住所、学校名を聞いておく。今日は警察沙汰にはしないが、家と学校へは報告しなければならないよ」
そう言うと、別の教員が私にそれを聞きにかかった。仕方なく、私は全てを正直に答えた。家の電話番号も聞かれた。
教員たちは我々を病院へ連れて行くか、否かを相談しているようであったが、私を含む六人の具合を改めて確認し、慎治の担任が、 「大丈夫やろ」 と他の先生にも同意を求めた。病院へ行くとなれば、警察へも報告しなければならないので、学校としてはできるだけそうはしたくなかったのであろう。私も警察問題になるのは嫌だったので、それはそれで結果としては有難いのだが、教員の処置は、生徒の体の心配よりも、学校の体面などを第一に考えているように思われ、はなはだ不快であった。
それに野次馬の人たちもどうかと思う。どうして、警察に連絡するなり、止(と)めようとする者が一人もいなかったのか。田舎では、こうはならない。警察にもすすんで連絡することはないが、必ず誰かが止めに入ってくる。この辺りが都会の冷たさなのであろうか。
慎治たち五人は先生の車に分乗させられ、どこかへ連れて行かれた。おそらくは彼らの学校か補導センターであろう。私は帰ってもよいということであったが、暫く呆然と立ちつくしていた。顔は腫れ、鼻血がこびりついていた。周りの野次馬たちが私を見て、何かひそひそ言い合っていた。私は彼らに激しい憤りを覚えたが、私のしたこともしたことなので、じっと我慢した。
「君、大丈夫か。病院へ行った方がいいんじゃないか」
おじさんがそう言うと、店員の女の人は心配そうに、私にハンカチを差しだした。
「有難うございます。大丈夫です。頭をやられていないので、どうもないと思います」
私はハンカチで顔の血を拭(ぬぐ)いながら、普段の言葉ではなく、標準語でそう答えた。
そうは言ったものの、顔は腫れ上がっていたし、今はまだ騒ぎの直後で気が張っていて、痛みはあまり感じないのだが、夜になれば、かなり痛くなるに違いなかった。
さすがにその日はジーンズを買う気にはならなかった。これでは一体何をしに、わざわざ列車に乗って和歌山まで来たのかわからなかったが、仕方がなかった。おじさんに迷惑をかけたことを詫び、近いうちに改めてジーンズを買いに来る旨を伝えた。そして、帰りの列車の時刻も教えて貰った。家へ帰ってからのことと、明くる日の学校のことを考えると、非常に憂鬱な気分になった。
家に着くと案の定、父と母が待ちかまえていた。もう報告がなされていたのだ。二人はまず私の体のことを心配してくれたが、母には、その後、こっぴどく叱られた。実は、今回一人で和歌山までジーンズを買いに行くことについては、母は大反対だったのだ。和歌山の荒れた事情を知っていたからだが、叔父について行ってもらうことを強く主張していたのだ。私の性格を知り抜いた上での、賢明な意見であった。そして、もろに母の懸念通りになってしまったのだから、理由は兎も角、私には反論の余地はなかった。ただ、父は一人で行くことに賛成してくれていた。 「男が十四、五にもなって、一人で和歌山くらい行けんでどうする」 と言って、母の反対を抑えつけてくれたのだ。 「あんたが賛成したりするさかい」 という、母の言葉には全く耳を貸す素振(そぶ)りはなく、父は私にこう言った。
「今回のことそのものは、仕方がない。お前も悪いことをしたとは思ってへんやろ。ただなあ」
父はそう言いながら、煙草に火をつけた。
「ただな、聡、これからはもう少し考えなあかんぞ。こんなことはせんに越したことはないんや」
父は決して怒っているわけではないが、諭すようにそう言った。私には父の言うことが正直あまりわからなかった。
「じゃあ、どうすればいいんよ」
「うん、そう言われても難しいんやけどなあ。今度のような者と対峙したときはな、できるだけ闘わんと勝つように考えるんや」
「闘わんと勝つ言うても」
「そうや、難しいこっちゃし、わしもお前にうまくよう説明せんが、歳とともに必ずわかるようになるはずや。また、そうならんと人間大きうなられへんのや」
父の言うことは、そのときの私には禅問答のようなもので、理解することは出来なかったが、 「人間が大きくなれない」 というところが、妙に気になった。そして、今回の喧嘩は、正直後味がよくなかった。これまでのそれとは明らかに違うのだ。何がどう違うのかは説明できないが、その説明できない部分に父の意味するところもあるのかもしれないと思った。大義名分は自分にある、と信じていたことすら、怪しく思えてきた。
「まあ、おいおい、また話したるから、今日は先に風呂へ行ってこい」
丁度そのとき叔父の家に遊びに行っていた弟が帰ってきた。私の腫れ上がった顔を見るなり、
「あれ、兄(にい)やん、顔どうしたんや。喧嘩で負けたんか」 と言った。
「阿呆、負けてへんわ。これから一緒に風呂へ行くぞ」 私は弟を連れて銭湯へ行った。
明くる日の学校も憂鬱なものであった。朝、授業の始まる前に職員室に呼び出された。担任と柔道部の栗山先生にこっぴどく叱られた。特に、栗山先生の方は、私が柔道の技をつかったか否かを聞いてきた。私が正直に言うと、
「お前は一体何のために柔道を習っているんや」 と言って、私の頭を拳骨で殴った。ただ、中学校ということで、それ以上の処分はなかった。これが高校であれば、謹慎くらいになっていたかもしれない。
教室でもクラスメートにさんざんからかわれた。
「おっ、聡、その顔どうしたんや。喧嘩でもしてやられたんか」 と、中野が言った。
「違うわ。負けてへんぞ。相手は五人やったんや。ごちゃごちゃ言うとったら叩くぞ」
「阿呆やなあ、中野叩いたら、お前また職員室へ呼び出しくうぞ」 隣にいた牧もそう言って、私を弄ぶ。女の子たちにも何やかやと言われたが、それより、私の机からかなり離れたところにいる一人の女の視線が気になって仕方がなかった。Mである。Mとは一年のときはクラスが別であったが、二年では同じクラスになっていた。一年前、 「聡くん、喧嘩ばっかり、バカみたい」 と言われて以来、必要最小限のことしか話をしていなかったが、彼女への私の思いは変わっていなかった。 「この顔を見て、また軽蔑しとるんやろうなあ」 そう思うと、いたたまれなかった。彼女はじっとこちらを眺めているが、何も言わない。それが私には、よけいにこたえた。
一週間後の日曜日、叔父の車に乗せて貰って和歌山へリーを買いに行った。私の両親は運転免許を持っていないので、こういうときはいつも叔父の世話になる。叔父と一緒に、先週行った、あの店へ再び行ったのである。この前は、あんな騒ぎになってしまって買えなかったので、嬉しさもひとしおだった。
リーのジーンズには色だけでなく、シルエットも何通りかあった。私は少し迷ったが、やや太めのワンウォッシュにした。店員の女の人が裾上げをしてくれている間に、おじさんに先週の喧嘩騒ぎのことを改めて詫びた。おじさんは愛想よく、何もなかったかのように接してくれた。帰り際に、女の人に借りていたハンカチを返そうとしたが、彼女は、 「いいわ、それ君にあげるよ」 と言った。この間はあんな騒ぎで気がつかなかったのだが、よく見ればかなり綺麗な女性であった。歳は私より五つくらい上であろうか。私は厚意に甘えて、ハンカチは頂くことにした。暫くの間それは私の宝物の一つであった。
リーのジーンズの穿き心地は最高であった。中尾先輩が穿いていたものより少し太めであったが、私はその太いところが特に気に入った。口の悪い同級生たちは、陰で、 「おい、聡なあ、ドラム缶みたいなジーパン穿いてるぞ」 と言っていたが、そんなことは全く気にならず、 「ふふ、お前らにはこのジーンズの良さがわからんやろ、これはジーンズや。お前らのはジーパンや」 と嘘ぶいてやった。
おじいさんに貰ったお金が少し余っていたので、近くの店で、できるだけリーに合いそうなベルトを買い求めた。ベルト通しを兼ねているラベルの内側へベルトを通したときの感激は、今もはっきりと憶えている。以来私は三十年以上ジーンズはリーしか穿いたことはない。そして、嬉しいことには、中学三年頃になると有田にもジーンズの本格的な専門店ができ、リーのジーンズもそこで手に入るようになった。
中学三年になると、私の生活の中心は勉強と柔道になっていた。ガキ大将の私が勉強を、と思われるかもしれないが、生来、異常なほどの負け嫌いなのである。喧嘩同様、勉強でも誰にも負けたくなかった。テスト前などはかなりハードにやり込んで、成績も良かった。 柔道の方は、これはもう、我が柔道部は県下でも群を抜いて強くなっていた。どれだけ強かったか、一つ例を挙げてみよう。今はどうかは知らないが、私が中学生の頃は、県大会が春と夏の二回あった。春の方は団体戦だけであるが、そのかわり、中学校だけではなく、町道場も、中学生だけの構成であれば出場することができた。その上、一校あるいは一道場につき、二チームまで出ることを許された。実際に二チーム参加したのは箕島中学校を含む四つの学校または道場しかなかったが、とにかく結構大規模な大会であった。 その大会の決勝戦が箕島中学校Aチームと箕島中学校Bチームなのである。つまり、当時の箕島中学校はレギュラーの五人以外の、控えの選手五人が出ても県で優勝できるほど強かったということだ。そして、その決勝戦は5ー0で我々Aチームの勝利であった。
夏の大会も圧倒的な強さで制し、私たちは憧れの講道館へ行くことができた。全国大会出場である。二年前の栗山先生の言葉、 「三年では全国を狙う」 というのが正(まさ)しく実現したわけだ。全国大会では予選リーグは難なく突破したものの、決勝トーナメントの二回戦で、優勝候補の一角である九州の強豪とあたり、残念ながら敗れてしまった。入賞できなかったのだ。それでも、和歌山に箕島中学校あり、と全国に知らしめることは十分できたと思う。因みに、我々の同期で有名な選手には、あの世界の山下こと山下泰裕をあと一歩のところまで追い詰め、オリンピックでも金メダルを取った斉藤仁(国士舘)や、後に大相撲へ行った服部らがいる。
夏の大会で柔道もひとまず終わり、あとは受験勉強まっしぐらという時期になった。この頃になってようやく私は、少し大人しく、というか一皮むけてきたようだった。つまらないことで喧嘩もしなくなってきた。一年前の和歌山での喧嘩の後で父に言われたことを理解するにはまだまだ至らなかったが、父の望んでいる方向へ進んでいるような気はしてきた。そして、なんと、あろうことか二学期の学級委員の選挙では委員長に選ばれてしまった。担任の大宝(おおたから)先生にも、 「聡、期待しとるぞ」 と言われた。この先生には現在もいろいろと世話になることが多い。
それは兎も角、私自身は少し煩わしくも思ったが、父と母は泣いて喜んだ。 「ガキ大将だったお前でも、少しは皆から信頼されるようになったのかもしれないぞ」 父はそう言って、嬉しそうな顔をした。
十月のある日のことであった。放課後、私は友人との話に時間を費やし、帰るのが遅くなった。急いで自転車置き場へ行くと、そこにMが立っていた。Mとは二年のときクラスが一緒だったが、三年ではまた別々になっていた。私が暫く黙っているとMの方から話しかけてきた。
「聡くんもう帰るの?」
「ああ、帰るよ。話してて、ちょっと遅うなってしまったんや。どうしたん?」
彼女も私と同じ自転車通学なのだが、今朝家を出るときに自転車がパンクしていたので、家の者に車で送ってきて貰ったようだ。帰りは、家が近い、クラスメートの明美の自転車に乗せて貰う約束になっていたのが、Mの方にクラブの用事が出来たので、明美は先に帰ってしまったらしい。
「帰るんだったら乗せてって欲しいんだけど、嫌(いや)?」
嫌なことなどあろうはずがない。小学校のときからずっと仄(ほの)かな恋心を抱いているのだ。 「これは夢ではなかろうか」 私は彼女に気づかれないように頬をつねってみた。実に痛い。力を入れすぎてしまった。そうだ、夢ではない。私は嬉しさのあまり、暫く返事ができなかった。
「嫌なのね。そうよね、私一年のとき聡くんにきついこと言ったもんね」
私は慌てて口を開いた。
「いや、嫌じゃないよ。僕の自転車でええんか」
彼女はにっこり笑って、 「うん、乗せてくれる?」 と言った。私は自転車置き場から自転車を取り出して、彼女の前まで出た。
「有難う。聡くん、もう一つお願いがあるんだけどなあ」
私の心臓は、もはや破裂寸前であった。好きな女の子と面と向かって話をするのは、プロレスラーと闘うのより度胸がいると思った。 「な、何や」
「聡くん、ジーパンのこと詳しいよね」
「いや、詳しいっていうことないけど、好きやなあ」
「あのね、私もジーパンが欲しいの。でも、何も知らないから、今度の日曜日一緒に店へ行ってくれない?」
「そ、それは、もしかしたら、デートというものではなかろうか」 そう思って、私はもう一度、自分の頬をつねってみた。さっきよりも力を入れすぎてしまったようだ。滅茶苦茶痛い。やはり夢ではなさそうだ。
「ねえ、さっきから何してるの?」
「い、いや、何でもない。今度に日曜日か」
「・・・・?」
私の言葉は、文法的にも支離滅裂であった。 「いかん、落ち着け。相手はたかが女の子じゃないか、レスラーではないぞ」
そう念じながら、何とか私は態勢を立て直して、Mに言った。
「いいよ。次の日曜日は特に用事もないし、僕でよかったらついて行ってやるよ」 それが精一杯の言葉であった。
「えっ、本当?有難う。じゃあ、ここへ座るね」 そう言って彼女は、横座りの、女の子独特の恰好で、私の自転車の後部座席に先に座った。私は両手でバランスをとりながら前に座った。後ろから、 「聡くん、何か一、二年前とは別人みたい」 と彼女は言ったが、私は敢えて返事をしなかった、いや、できなかった。自転車を漕ぎ出すと、彼女は私の腹に両腕を回して、落っこちないようにした。
「うわあ、凄い。何?このお腹(なか)は」
その頃の私は柔道のためもあって、家でも時間さえあれば腕立て伏せや腹筋運動ばかりしていたので、大胸筋は盛り上がり、腹筋もくっきりと割れていた。胸の方は兎も角、腹は今では見る影もないほど脂肪が巻き付いているが。
私にも少し余裕ができてきた。
「よし、飛ばすで。振り落とされんようにしっかり捉(つか)まっとけよ」
「無茶しないでね」
小柄なMを乗せて走るのはたやすいことだったが、私は自分の言葉とは裏腹に、できるだけゆっくりと自転車を漕いだ。空は薄暗がりになり、夕陽が沈みかけていたが、家までの道が、このまま永遠に続いてくれないものかと思った。
了